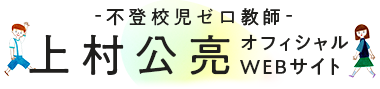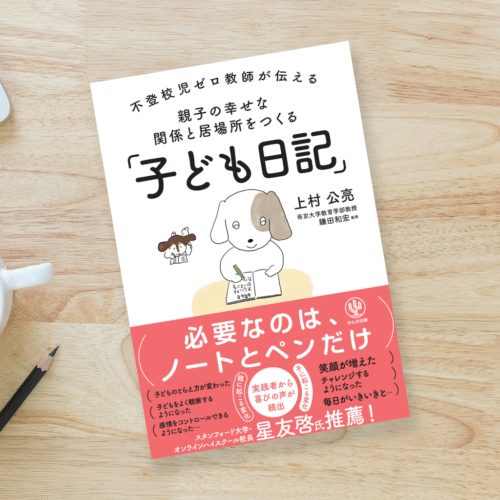命を削ってでもやりたいこと

思いがあって学校教育に戻ってきたその根底にある思いは何なのか、それを自問自答していました。
11ヶ月前、勤めていた児童発達支援・放課後等デイサービスを会社都合退職となり、ハローワークに通ったあの時期。教員に戻ることを決断した自分でも分からない隠れた思い。
それは適応障害と診断されたあの頃の思いとは全く違っていました。よい授業を創って研究会で発表することや、学校組織の活性化のために時間を費やして職場を盛り上げようとしていた横浜のときの働き方とは大きく違っていました。
それより、過去の自分と同じように苦しんでいる先生達のサポートをしたい。自分が経験したことだったら、どんどんオープンに話して、「助けて!」とか「困った!」って言ってほしい、そんな思いでした。
教育委員会へ伝えたのは、学級担任はやれないということ。外からサポートすることに徹したいと話しました。
結果的には療養休暇に入った先生の穴を埋める役割を担うことができました。でも、ふと立ち止まって、ひとつの学校が何とか回せたとしても他校は?全国では?と、広く見ようとすると自分の経験してきた苦しみをもっともっと発信していく必要があるように感じました。
先生達が学校に来れないのと同時に子ども達も学校に来れない子が増えている。これは日本の学校教育の大きな課題です。
結果的に実績として誇れるのは、上村級から一人も不登校を出したことがないこと。
学校に行くことがいいことだとも思っていないし、不登校がダメだと思っているわけではありません。むしろ、年々その見方は自分なりに緩和して、行かないことを選ぶことはありだとさえ思っています。
でも、行きたいのに行けない子、そんな家庭へのサポートはとっても必要だと感じています。心に傷を負った子へのサポートは、あの日行きたくても行けなくなった自分自身とも重なり、何とかしたいという思いに駆られるのだと思います。
自分は学校という場所が好きです。いろんな思いをもつ子が居て、そんな子達と授業をしたり、そんな子達の話を聞いたりするのが好きです。そして、家庭訪問や面談も好きです。学校とは違う家での様子、親御さんとのお話も、この子のことを分かりきることはないけれど、少しまた知れる気がして好きです。
でも、学校は変です。特性を理解せずに集団に無理矢理合わせようとしたり、学習指導要領の内容だって多すぎたりして子どもを傷つけます。テストの点数で比べたり、成績表のAの数を比べたり、そもそも年齢で区切ることすらどうなの?と思います。多数派に合わせることを強いられ、苦しむ子。そんな子や家庭のサポートをしたい思いで、「この子キャリア応援団」を立ち上げました。その先にある思いは、子どもも先生も安心して通える学校を増やしたいという思いな気がしてきました。
命を削ってでもやりたいこと
まだ自問自答は続けますが、今日現在ではそんな思いです。思いに賛同し、正会員、賛助会員になってくださった皆様、本当にありがとうございます。
明日から新年度。健康保険も切り替わります。新たなスタートを、これまで出会った思いに共感した皆さんと切れること、本当に感謝です。
組織が持続するには運営資金も必要で、そして賛同者が多ければ多いほど変な学校を変えていけると思います。是非、身近な人からこんな思いをもった人が立ち上げた団体があるよと知らせていただき、仲間を増やしていただけたら嬉しいです。